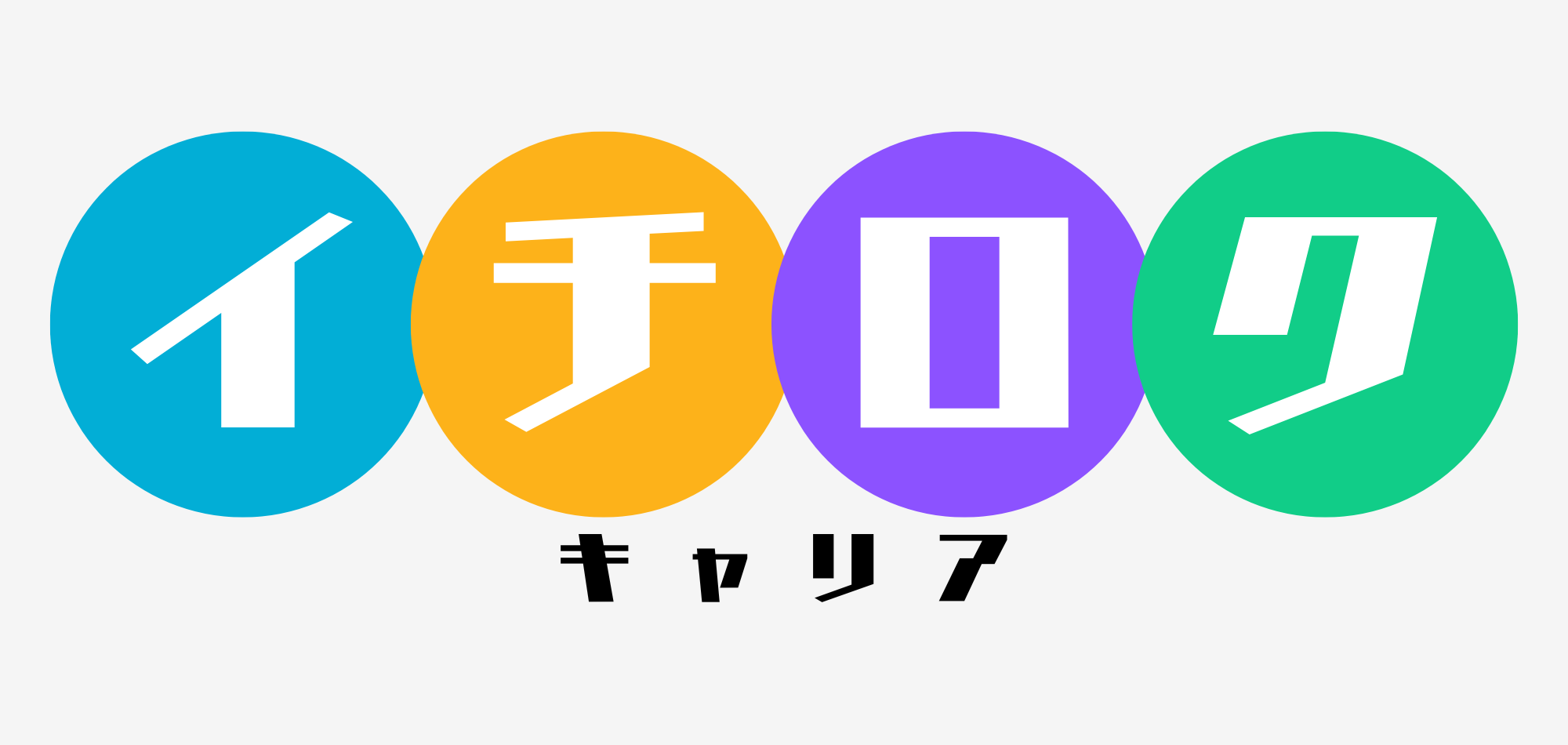※正しいMBTIタイプの分析・診断は、MBTI認定ユーザーのもと必ず対面で行われる必要があります。また、本サイトに掲載しているMBTIタイプの特徴は、本サイト編集部のリサーチに基づく一般的な情報です。あくまで参考情報としてご参照ください。
※MBTIに関する情報は一般社団法人日本MBTI協会からご覧いただけます。
※「MBTI」は一般社団法人日本MBTI協会に商標登録されています。
MBTI×メンヘラ度ランキング|タイプ別の特徴と対処法

MBTIタイプとメンヘラ傾向の関連性に興味をお持ちの方も多いのではないでしょうか。この記事では、各タイプのメンヘラ度をランキング形式で紹介します。
自分のタイプの特徴を知ることで、メンタルヘルスの改善に役立つヒントが得られるかもしれません。タイプ別の対処法も解説しているので、ぜひ最後までお読みください。
MBTIタイプ別メンヘラ度ランキング TOP8
MBTIの各タイプには、メンヘラ傾向の強さに違いがあります。感情の起伏が激しいINFPから、他人の評価を気にしすぎるESFJまで、上位8タイプの特徴と傾向を詳しく見ていきましょう。各タイプの弱点を理解することで、自己理解や他者との関係性の改善に役立てることができます。
1位:INFP(仲介者)|感情に流されやすく依存的
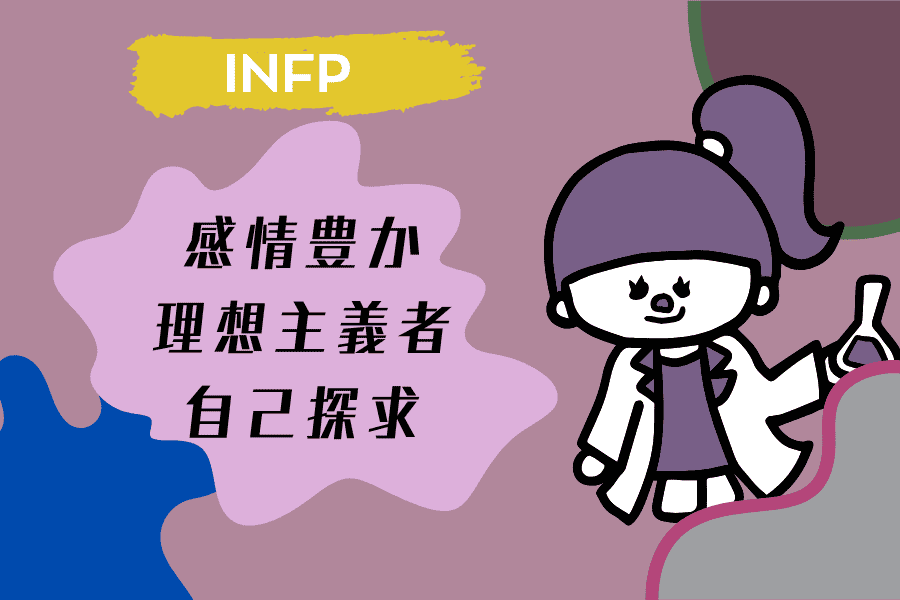
- 感情の起伏が激しく共感力が高い
- 理想主義が現実とのギャップを生む
- 承認欲求が強く依存傾向がある
INFPタイプは、豊かな感受性と共感力を持ち、感情の起伏が激しい特徴があります。この性格は人間関係において深い絆を生みますが、周囲の言動に過敏に反応してしまう場面も少なくありません。また、理想主義的な性格から現実とのギャップに悩みやすく、完璧を求めることで自己批判に陥りやすい傾向があります。
さらに、承認欲求が強く他者への依存傾向が見られることも特徴の一つです。自分の価値観を見失い、他者からの評価に頼りがちなため、自立した自己肯定感の構築が課題となります。
INFPの感情管理を助けるためには、感情を言葉にして客観視することや、小さな目標設定を通じて成功体験を積み重ねる方法が効果的です。さらに、自己肯定感を高めるために自己対話を意識的に行うことも重要です。これらの取り組みを通じて、健全な自己認識と人間関係の構築が可能になります。
2位:ISFP(冒険家)|感受性が強く自己否定的
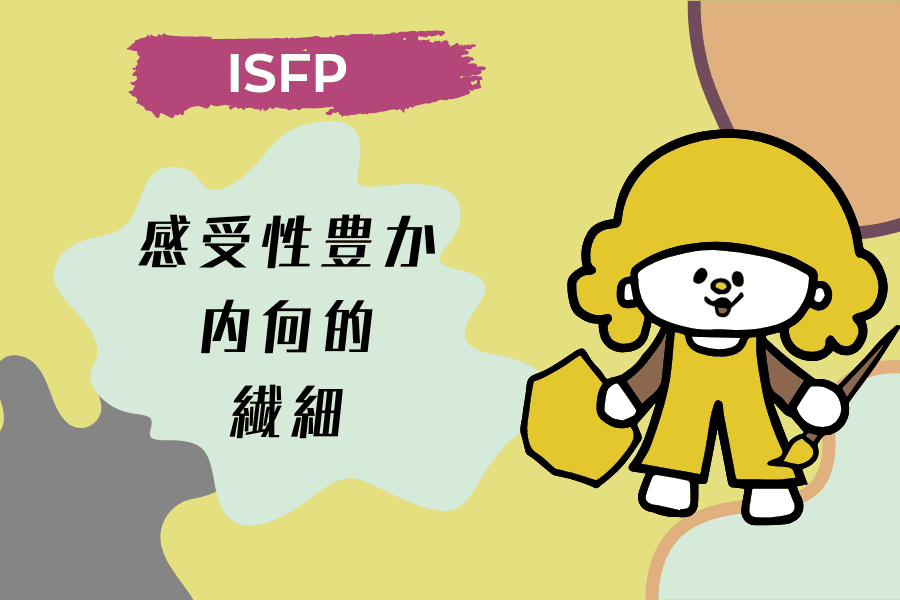
- 他者評価に敏感で自己否定的
- 感情を抑え込みストレスを抱えやすい
- 理想と現実のギャップに悩む
ISFPは繊細な感受性を持ち、周囲の感情や雰囲気を敏感に察知します。この能力は他者に寄り添う力となりますが、同時に他者評価に過剰に影響され、自分に厳しい基準を設けがちです。その結果、自己否定的な思考に陥りやすくなります。
また、感情を内に秘める傾向が強く自己表現が苦手なため、ストレスを抱えやすいのも特徴です。この抑圧された感情は、不安や突発的な感情の爆発につながることがあります。さらに、冒険を求める性格と現実の制約とのギャップにより、不満や悩みが生じることも少なくありません。
ISFPの魅力を引き出すためには、感情を適切に表現し自分の価値を再確認することが重要です。理想と現実のバランスを意識し、内に秘めた感情や思考を他者と共有する努力をすることで、心の安定が図れるでしょう。
3位:ENFP(広報運動家)|感情起伏が激しく不安定
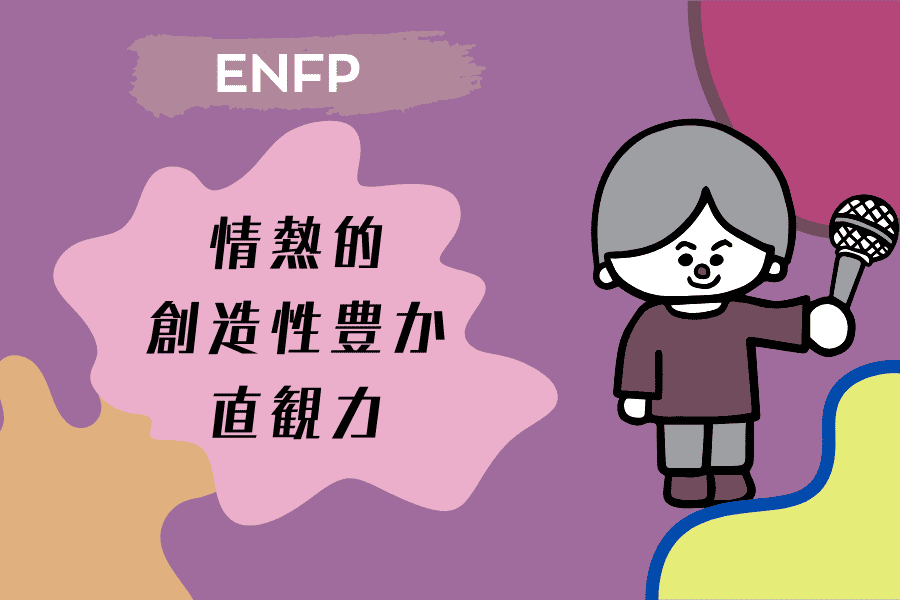
- 感情の起伏が激しく影響を受けやすい
- 理想追求が現実とのギャップを生む
- 新しい刺激を求め衝動的になる
ENFPタイプは、感受性の高さと想像力の豊かさから、感情の起伏が激しい特徴があります。喜びや悲しみを大きく感じ、その感情を周囲に伝えることで魅力的に映る反面、時には相手を戸惑わせることもあります。感情表現が豊かなため対人関係に深みを与えますが、不安定さも伴う場合があります。
理想を追求する姿勢はENFPの強みですが、現実とのギャップを認識した際に落胆しやすい点が課題です。また、新しい刺激や経験を求める衝動的な行動が、結果として不安定さを増幅させる場合もあります。
ENFPの感情を安定させるには、感情の波を理解し、瞑想やジャーナリングを取り入れることが効果的です。また、現実的な目標を設定し、段階的なアプローチで達成を目指すことで、不安定さを軽減できます。
新しい刺激を求める特性を適切に管理することで、創造性を活かしつつ安定した生活を築けるでしょう。
4位:ESFP(エンターテイナー)|衝動的で自己中心的

- 衝動的な行動で後悔しやすい
- 自己中心的な振る舞いで孤立する
- 刺激追求が依存を招く可能性
ESFPタイプは、その場を盛り上げる明るさと社交性が魅力ですが、衝動的な行動が精神的な不安定さを引き起こすことがあります。感情や欲求に従って即行動に移す性格が、計画性の欠如や後悔を生む原因となります。これにより、自己嫌悪に陥りやすい面も見られます。
さらに、自己中心的な行動が対人関係に悪影響を与える場合があります。自分の欲求を優先しすぎると他者の気持ちを軽視する結果となり、周囲との摩擦や孤立を招くこともあります。このような状況が、不安感や孤独感を引き起こす要因になります。
刺激を求める性格が依存傾向を高める可能性もあります。新しい体験を追求する姿勢は魅力的ですが、過剰になるとアルコールや薬物などへの依存に繋がるリスクが高まります。
ESFPがこれらの傾向を克服するためには、自己認識を深め、感情や行動をコントロールする習慣を持つことが重要です。他者の感情に配慮しバランスの取れたコミュニケーションを心がけることで、健全な人間関係を築くことができるでしょう。
5位:ESTJ(幹部)|完璧主義でストレスを抱えやすい
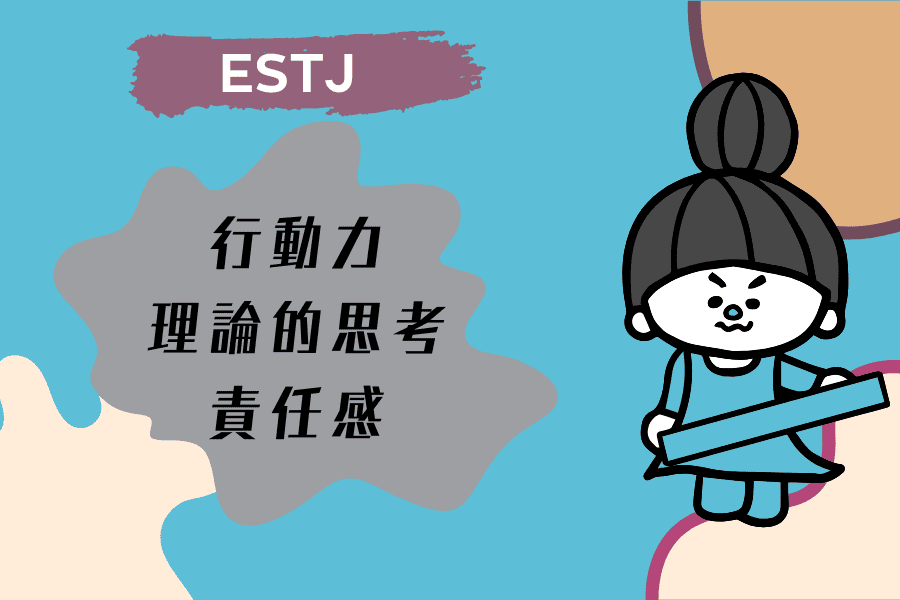
- 完璧主義で自己批判が強い
- 責任感が強くバーンアウトしやすい
- 感情を溜め込みストレス増加
ESTJタイプは、その完璧主義的な性格が特徴で、ストレスを抱えやすい傾向があります。自分に高い基準を課し些細なミスも許さない姿勢が、過度の自己批判や不安感を引き起こす原因となります。この厳格さが時として心身の負担を増やします。
また、ESTJの強い責任感は仕事や義務を優先する姿勢を生み出しますが、自分の健康や私生活を犠牲にすることもあります。その結果、バーンアウトに陥る可能性が高くなります。責任感が彼らの長所である一方、バランスを取ることが課題となります。
さらに、感情表現が苦手で、ストレスを内に溜め込みやすい傾向があります。この特性が人間関係や自己表現の場で問題を引き起こすこともあります。
ESTJタイプがストレスを軽減するためには、完璧を求めすぎず妥協を覚え、感情を認識して適切に表現する練習が必要です。また、定期的な休息を取り仕事以外の趣味や活動に時間を割くことで、心身の健康を保つことができます。
6位:ENFJ(主人公)|他者への過剰な配慮で疲弊
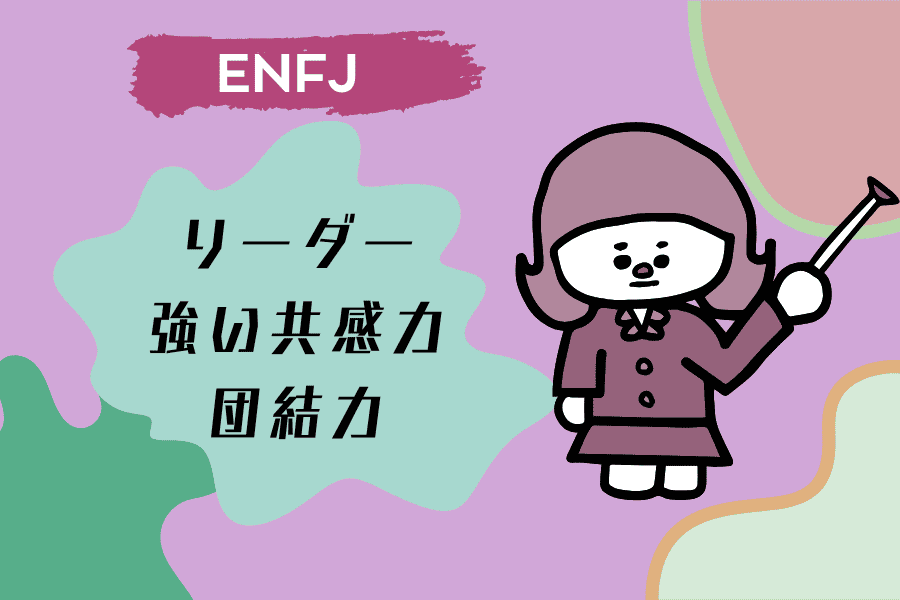
- 他者への過剰な配慮で疲労
- ネガティブ感情を吸収しやすい
- 自己ケアの習慣が必要
ENFJタイプは、他者への深い理解と配慮を持つ反面、その特性が自身を苦しめる要因となることがあります。彼らは周囲の期待に応えようと無理をしがちで、例えば友人の相談に深夜まで付き合い、自身の健康を犠牲にしてしまうことがよく見られます。
また、ENFJの高い共感能力は、他者の感情を吸収しやすい特性を持ちます。周囲のネガティブな感情に過度に影響されることで、精神的な疲弊を招く可能性があります。これにより、自分自身の感情や欲求を見失うリスクが高まります。
ENFJが心身の健康を保つには、自分の感情や欲求を確認する時間を持ち、自己ケアを優先することが必要です。さらに、他者の期待に応え続けるだけでなく、時には「ノー」と言う勇気を持つことが大切です。
これらの習慣を取り入れることで、ENFJは自身を大切にしながら、他者をより良い形で支援できるでしょう。
7位:INFJ(提唱者)|理想と現実のギャップに悩む
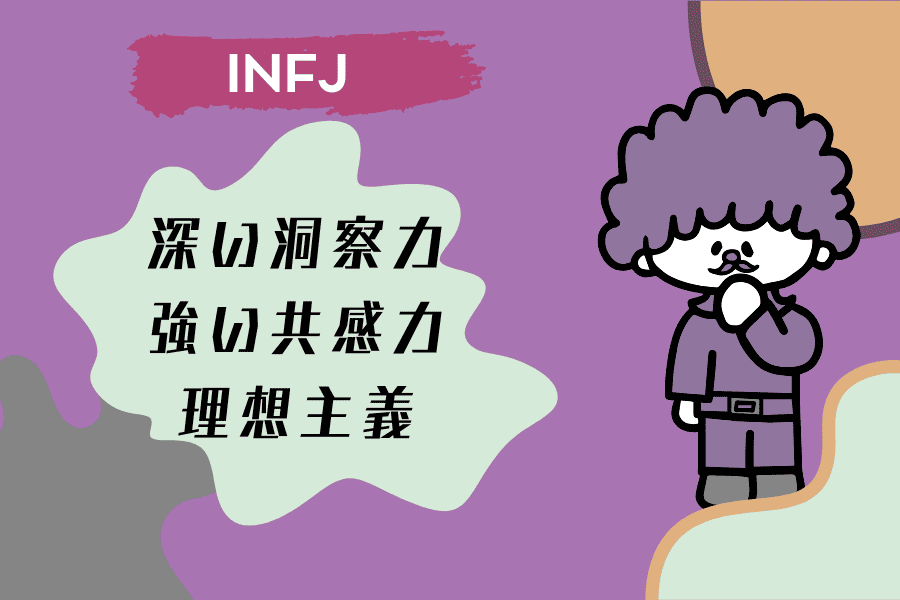
- 理想と現実の差に苦しむ
- 他者優先で自身を犠牲にしがち
- 完璧主義で自己批判が強い
INFJタイプは、強い理想主義と深い洞察力を持つ一方で、理想と現実のギャップに悩む傾向があります。理想的な世界像と現実社会の違いを受け入れることが難しく、この差異が自己否定や失望感を引き起こすことが少なくありません。
さらに、INFJは他者の感情を鋭く察知する能力を持っていますが、この特性が裏目に出る場合もあります。他人のニーズを優先するあまり、自身の欲求を後回しにしてしまい、精神的な疲労を蓄積させてしまいます。
完璧主義的な性格もINFJの特徴です。自分に高い基準を課し些細な失敗でも強い自己批判に陥るため、ストレスを感じやすい傾向があります。
INFJが健康的なメンタルを維持するには、理想と現実のバランスを取り、柔軟な思考を心がけることが大切です。また、自分の長所を認識して自己肯定感を高め、他者のニーズと自身のニーズのバランスを意識しながら行動するとよいでしょう。
これにより、INFJは自身の特性を活かしつつ、健全なメンタルを保てるようになります。
8位:ESFJ(領事官)|他人の評価を気にしすぎる

- 他人の評価を気にしすぎる
- 自己犠牲的な行動パターン
- 感情の抑圧でストレスが増加
ESFJタイプの方は、周囲との調和を重視するあまり、他人の評価に敏感になりがちです。この特性は自己価値観を外部評価に依存させ、精神的な不安定さを引き起こす原因となります。例えば、周囲の期待に応えようと無理を重ねることで、ストレスが蓄積しやすくなります。
また、ESFJの献身的な姿勢は、時として自己犠牲的な行動パターンを生み出します。自分の感情や欲求を後回しにし、他者のニーズを優先することが、長期的には精神的健康を損なう要因となります。さらに、不快な感情を抑える傾向があるため、ストレスが内に溜まりやすく、健康に悪影響を及ぼす可能性があります。
ESFJが健全なメンタルを維持するには、自己価値を他者の評価から切り離し、自分の感情や欲求を大切にすることが重要です。完璧を求めすぎず、時には「ノー」と言える勇気を持つことが、より健康的な対人関係と自己認識の形成に役立つでしょう。
MBTIタイプ別メンヘラ度ランキング 9位~16位
MBTIの16タイプのうち、比較的メンヘラ度が低いとされる9位から16位までのタイプを紹介します。各タイプの特徴や傾向、精神的な課題について解説していきます。自己犠牲的なISFJから衝動的なESTPまで、それぞれの性格がどのように精神状態に影響を与えるのか、詳しく見ていきましょう。
9位:ISFJ(擁護者)|自己犠牲的で燃え尽きやすい
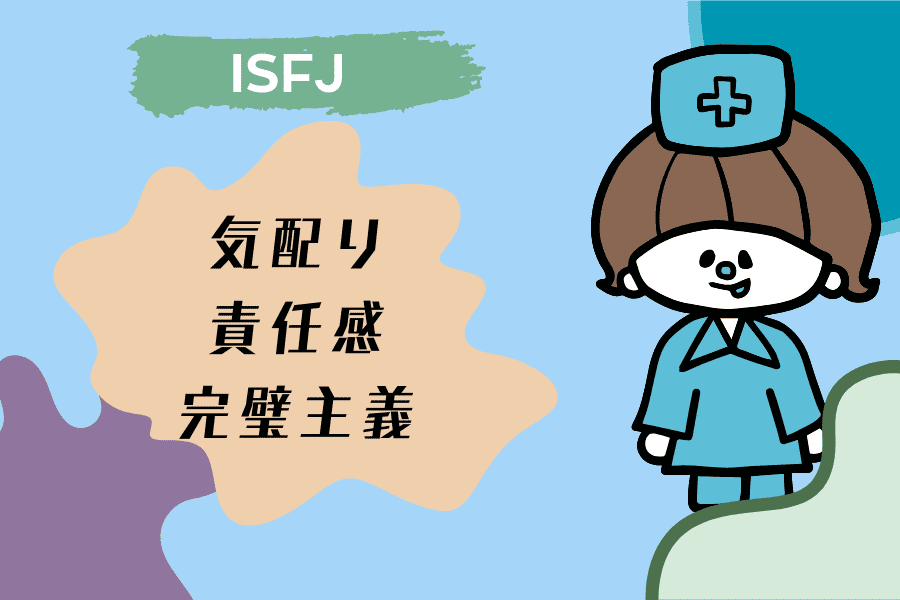
- 他者優先で自己犠牲的
- 完璧主義で自己批判が強い
- バーンアウトや精神的疲労のリスク
ISFJタイプの方は、周囲への気遣いや責任感から自己犠牲的な行動をしがちです。他者のニーズを優先し、自身の健康やウェルビーイングを後回しにするため、短期的には感謝されても長期的には問題を引き起こすことがあります。強い奉仕精神は、時として自分の限界を超えた働きを生み、休息を取らずに働き続けることでバーンアウトのリスクが高まります。
また、ISFJは完璧主義的な傾向を持ち、些細なミスでも自己批判に陥りやすいです。常に高い基準を課すことで、精神的疲労が蓄積される危険性があります。自身のメンタルヘルスを守るためには、自己犠牲的な行動を見直し、適度に休息や自己ケアを取り入れることが重要です。
10位:INTJ(建築家)|孤独を感じやすく自閉的
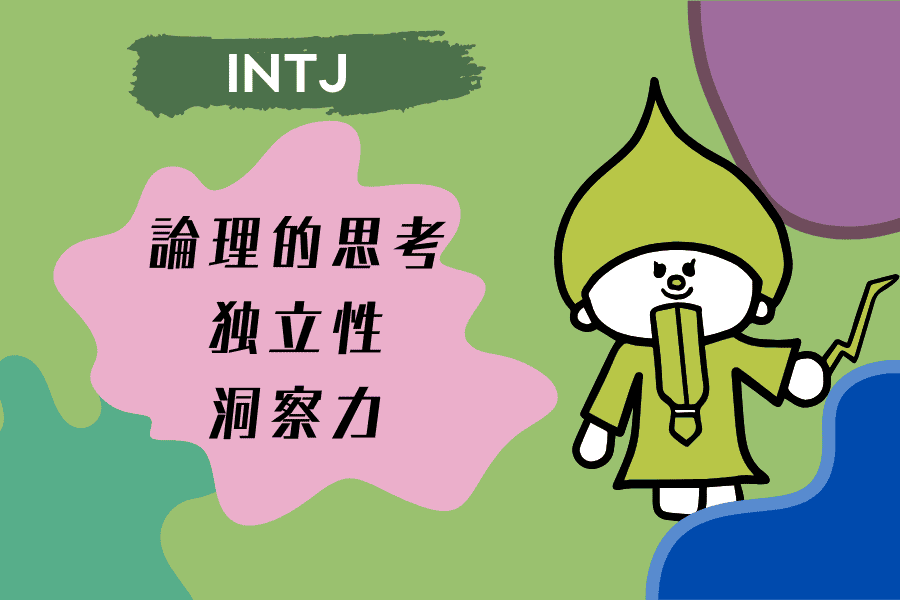
- 社会的孤立感を抱えやすい
- 完璧主義がストレス要因になる
- 内面に集中し過ぎる傾向
INTJタイプは、論理的で独創性が高い一方で、社会的孤立感を抱えやすい性格です。内向的な性質が強く、他者との交流を避ける傾向があるため、長期的には孤独を感じる可能性が高まります。
また、完璧主義的な思考が強く、自分に高い基準を課し過ぎることがあります。このため、目標が達成できない場合に過度のストレスや自己批判を招く場合が多いです。
内面世界に集中し過ぎることも、精神的な負担を強める要因となります。柔軟な姿勢を持ち、社会的なつながりを意識的に増やすことが重要です。
11位:ENTJ(指揮者)|支配欲が強くストレスを溜める
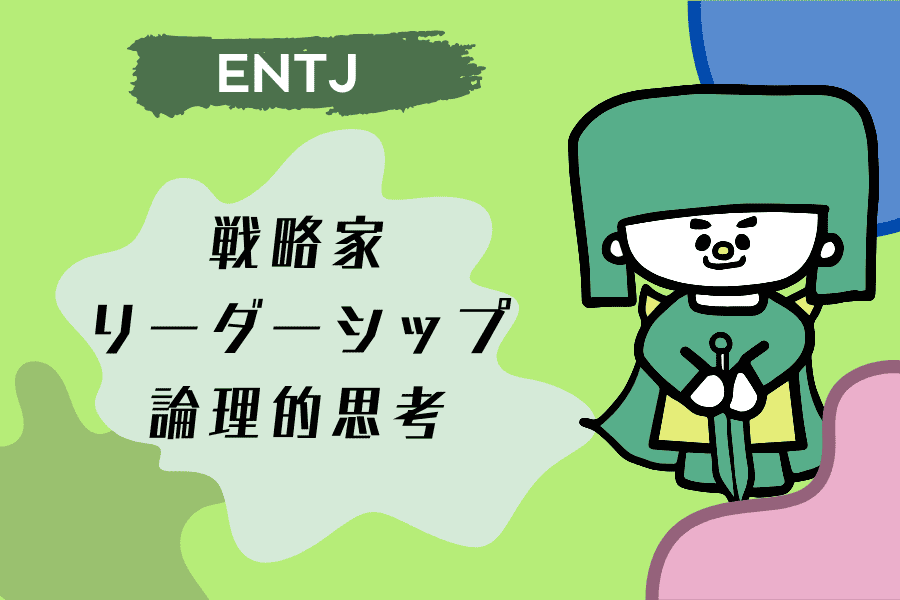
- 支配欲がストレスの原因になる
- 完璧主義が周囲と軋轢を生む
- 感情表現が苦手で葛藤を抱える
ENTJタイプは、指導力と戦略的思考に優れる反面、支配欲の強さがストレスの原因になりやすい性格です。目標達成に執着するあまり、自分や他者に過度な要求をしてしまう場合があります。これが周囲との摩擦や自身の精神的負担につながります。
さらに、完璧主義的な傾向が強いため、非現実的な基準を追求してしまうことが少なくありません。結果として、チームの士気が低下したり、自分自身が疲労を感じやすくなります。
感情表現が苦手であることも、ENTJの特徴です。ストレスをうまく発散できないことが多く、内面的な葛藤を深める場合があります。柔軟な姿勢を持ち、感情を共有する場を意識的に作ることが重要です。
12位:INTP(論理学者)|社会適応に苦労し孤立しがち
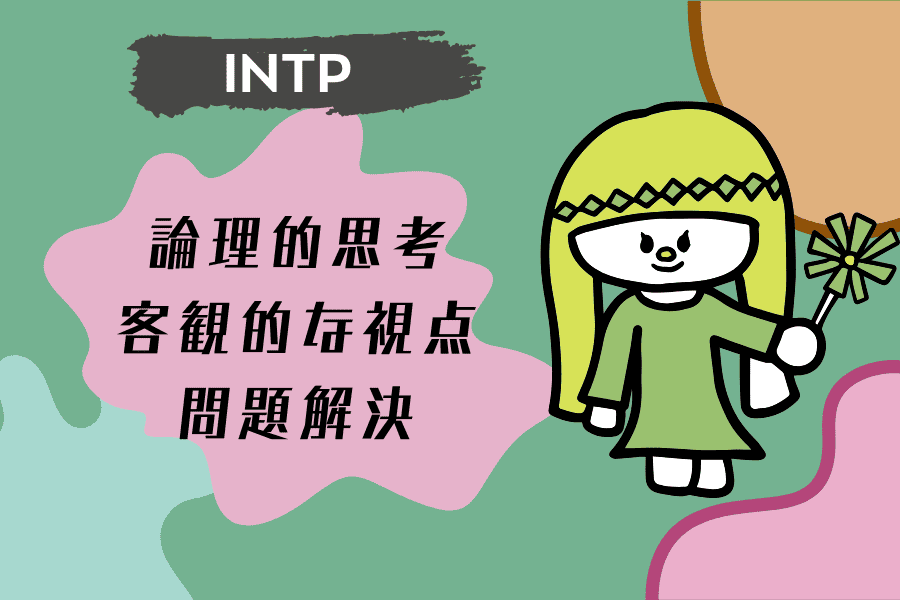
- 社会適応に苦労し孤立しやすい
- 感情的な会話が苦手で関係を築きにくい
- 内面に没頭し交流を疎かにする
INTPタイプは、論理的思考に優れている一方で、社会適応に苦労し孤立しやすい特徴を持っています。現実社会の曖昧さや非合理性に違和感を覚えやすく、職場や人間関係で孤独感を感じる場合が多いです。
感情的な会話や雑談を苦手とし論理的な議論を好むため、対人関係の構築が難航することがあります。この傾向が疎外感を深め、孤独を感じやすくさせています。
また、内向的で独立心が強いため、自分の内面世界に没頭しすぎる傾向があります。周囲との交流を避けがちであるため、孤立が悪循環を生む場合があります。論理と感情のバランスを意識することが重要です。
13位:ENTP(討論者)|批判的で対人関係を崩しやすい
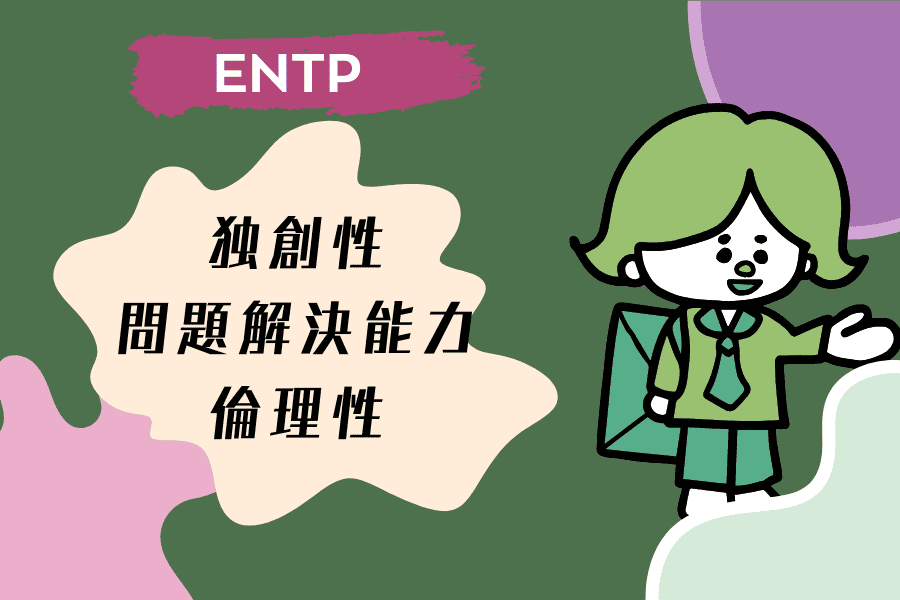
- 批判的思考で関係を悪化させる
- 理想と現実のギャップに悩む
- 感情表現が苦手でストレスを抱える
ENTPタイプは、論理的思考と批判的な分析力を持つ一方で、対人関係を悪化させやすい傾向があります。他者の意見に対し鋭い指摘を行うため、無意識に相手を傷つけてしまう場面が少なくありません。
また、創造性が高く新しいアイデアを追求する性質が強いため、現実とのギャップに直面することがあります。このギャップがフラストレーションを生み出しやすい要因となっています。
さらに、論理を重視するあまり感情表現が苦手です。この特性がストレスを溜めやすくし、内面的な葛藤を引き起こす場合があります。柔軟な姿勢を意識することで、精神的な安定を保ちやすくなるでしょう。
14位:ISTJ(管理者)|変化を受け入れられず不安定に
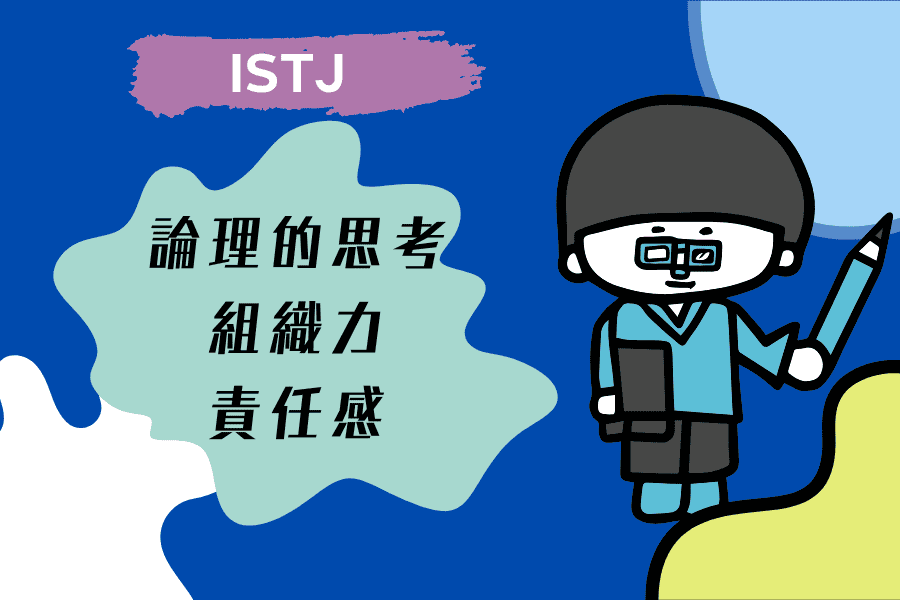
- 変化への適応が苦手で不安定になる
- 問題を抱え込み孤立しやすい
- 確立された秩序に執着しやすい
ISTJタイプは、秩序を重んじる性格から、変化への適応が苦手で精神的に不安定になりやすい傾向があります。突然の組織改編や生活環境の変化は、大きなストレス要因となる場合があります。変化に対する抵抗感が不安や焦りを生み出し、適応を難しくすることがあります。
また、内向的な特徴が強いため、不安や戸惑いを他者と分かち合うことに抵抗を感じやすいです。その結果、問題を一人で抱え込み、孤立感がさらに不安定さを悪化させる場合があります。
ISTJタイプが精神的安定を保つには、変化を段階的に受け入れる努力が必要です。信頼できる人とのコミュニケーションを通じて、新しい経験に少しずつ慣れることが重要です。柔軟性を養うことで、より安定した心理状態を目指せるでしょう。
15位:ISTP(巨匠)|感情表現が苦手で孤独を感じる
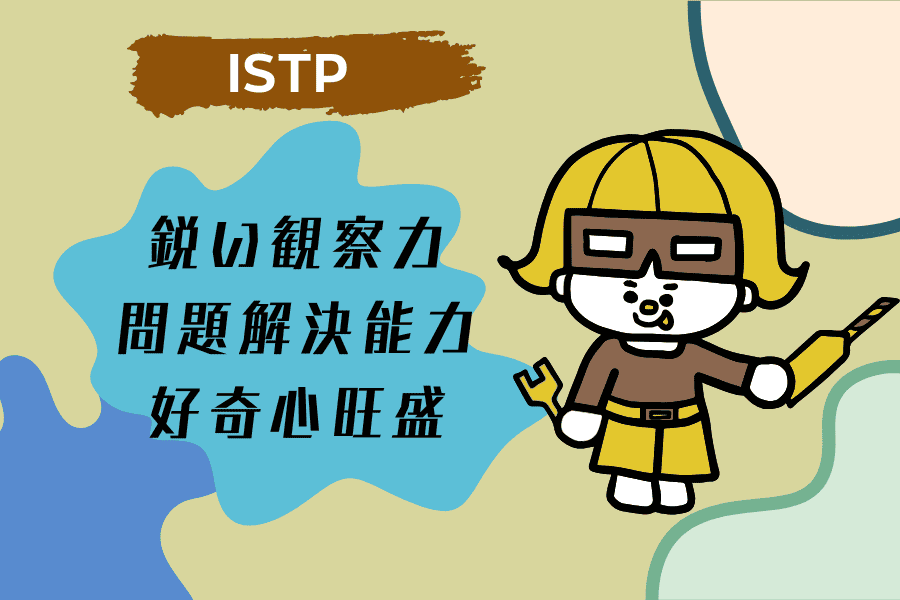
- 感情表現が苦手で誤解を招きやすい
- 深い関係を避け孤独感を抱えやすい
- 感情を論理的に分析しがち
ISTPタイプは、論理的思考を重視する性格のため、感情表現が苦手で誤解を招きやすい傾向があります。内面に複雑な感情を抱えていても、それを適切に言葉で伝えるのが難しく、対人関係で問題が生じる場合があります。
さらに、強い独立心を持ち、親密な関係を築くことに消極的です。自由を重視する性質が他者との深い交流を避ける結果を招き、長期的には孤独感や疎外感を感じるきっかけとなりやすいです。
また、感情を論理的に分析しようとするため、自己や他者の感情を十分に理解しきれない場合があります。これが精神的な孤立を深める原因となる可能性があります。感情表現や共感のスキルを意識的に高めることが重要です。
16位:ESTP(起業家)|衝動的行動で後悔しやすい
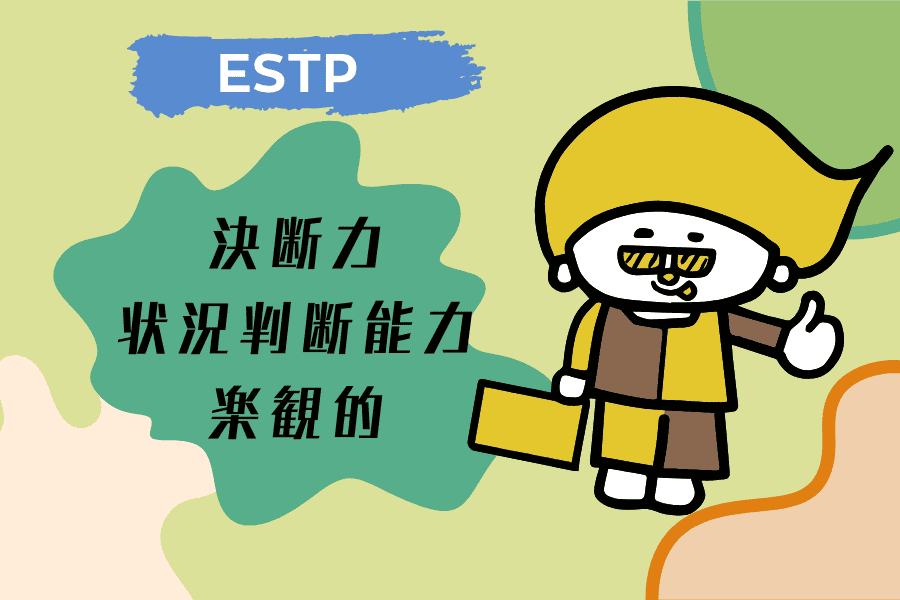
- 衝動的行動で後悔しやすい
- 刺激を求め危険な行動を取りがち
- 感情表現が苦手で葛藤を抱えやすい
ESTPタイプは、即断即決の性格が特徴で、衝動的な行動に走ることが多いです。この傾向が後悔を招き、精神的な不安定さにつながる場合があります。思慮深さよりも行動力を優先するため、十分な検討を欠いた決断を下しやすいです。
また、刺激を求める性質が強く、危険な行動や無計画な冒険に挑む場合があります。これが後悔や自己批判を引き起こし、不安定な心理状態を作り出す要因となります。
さらに、感情表現が苦手で、内面の葛藤を言葉にすることが難しい特徴があります。このため、ストレスを突発的な行動で発散しがちです。感情を他者と共有する意識を持つことが精神的な安定につながるでしょう。
まとめ
この記事では、MBTIの16タイプ別にメンヘラ度を分析し、ランキング形式で紹介しました。各タイプの特徴や傾向、メンヘラ化しやすい状況、そして対処法についても詳しく解説しています。
MBTIの理解を深めることで、自分や周囲の人々の行動パターンや思考の傾向をより良く把握できるでしょう。メンタルヘルスケアの参考にしてください。