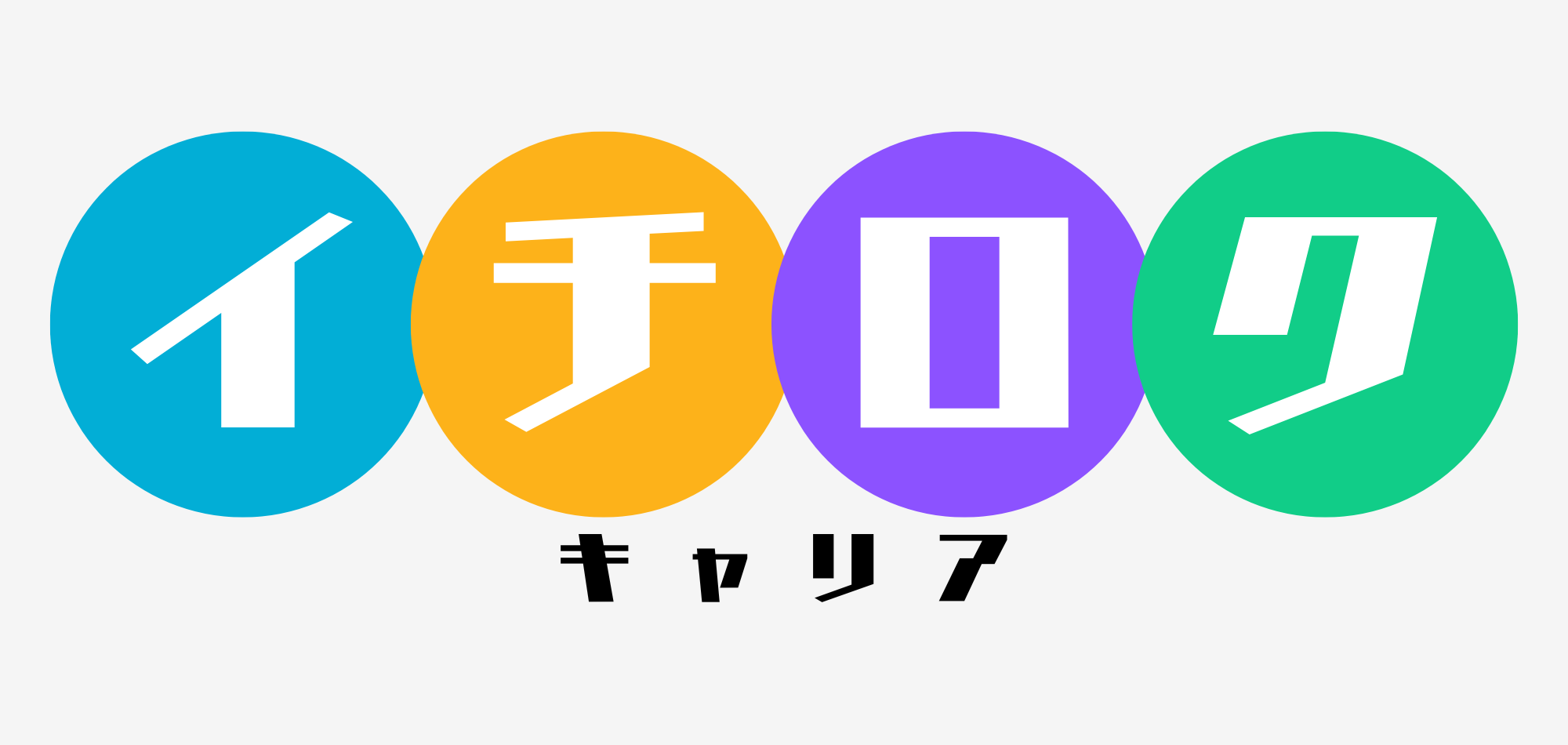※正しいMBTIタイプの分析・診断は、MBTI認定ユーザーのもと必ず対面で行われる必要があります。また、本サイトに掲載しているMBTIタイプの特徴は、本サイト編集部のリサーチに基づく一般的な情報です。あくまで参考情報としてご参照ください。
※MBTIに関する情報は一般社団法人日本MBTI協会からご覧いただけます。
※「MBTI」は一般社団法人日本MBTI協会に商標登録されています。
MBTI×社会不適合ランキング|特性を理解し強みを活かす秘訣

社会に馴染めない、人間関係がうまくいかない…。そんな悩みを抱える方は少なくありません。実は、あなたのMBTI特性が関係しているかもしれません。
この記事では、MBTI別の社会不適合ランキングを紹介し、各タイプの特徴と適応のコツを解説します。自分の強みを理解し、それを活かした社会適応の方法を見つけることができるでしょう。
あなたのMBTIタイプは何位?ランキングを確認して、自己理解を深めましょう。
MBTIで見る社会不適合ランキング TOP8|あなたの特性は?
MBTIの各タイプが持つ特性と社会適応の難しさについて、具体的な分析と対策を紹介します。理想主義的なINFPから議論好きなENTPまで、8つの性格タイプの課題と強みを探ります。
自分の特性を理解し、社会との調和を図るヒントを見つけましょう。
1位:INFP(仲介者)|理想と現実のギャップに悩む
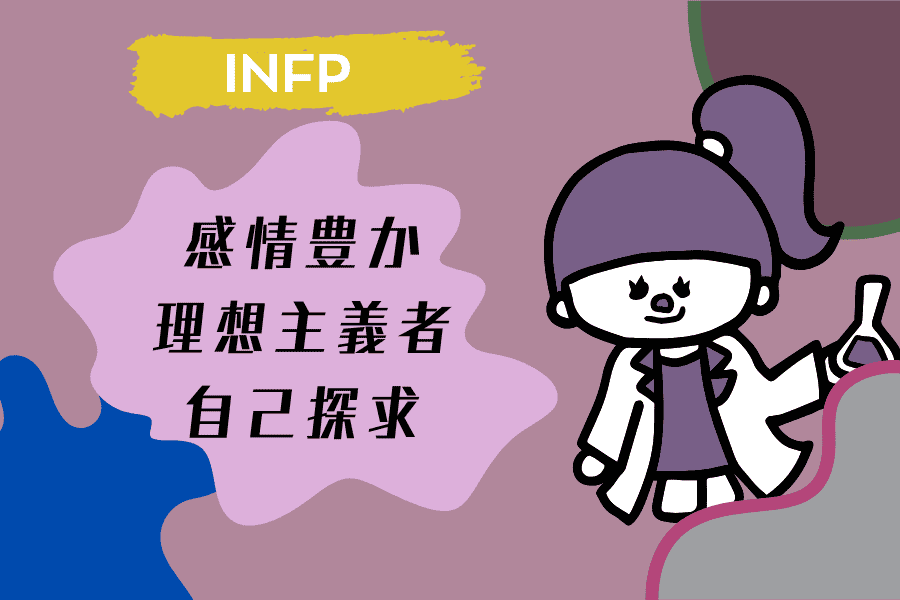
- 理想主義的な価値観を大切にする
- 現実とのギャップに悩むことがある
- 他者の感情に敏感で調和を重視する
INFPは理想を追い求める性格から、価値観や信念を強く大切にする傾向があります。一方で、現実の制約や他者との価値観の違いに苦しむことがあり、特に職場環境などで理想と現実のギャップに悩む場合があります。他者の感情に敏感なた周囲との調和を重視しますが、信念との葛藤が負担になることもあります。
創造的な分野で自己表現の場を作ることや、柔軟に妥協点を見出す姿勢を持つことが鍵です。理想と現実のバランスを意識するため、マインドフルネスの実践を取り入れると良いでしょう。自分の価値観を守りつつ、社会と調和を図ることで成長につながります。
2位:ISFP(冒険家)|ルールや制約を嫌う自由人
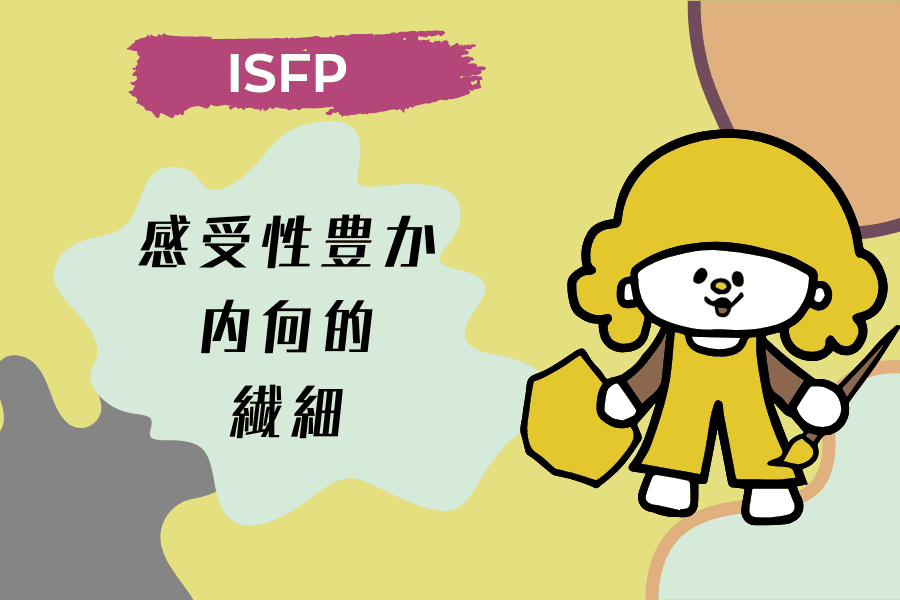
- 自由を重視し、ルールや制約を嫌う
- 柔軟性が高く、新しい環境に適応できる
- 感覚的な体験や価値観を大切にする
ISFPは自由を最優先する性格から、決まりきったルールや制約に違和感を覚えやすい特徴があります。柔軟性が高く新しい環境にも適応できる一方で、厳格な勤務時間や規則が多い職場ではストレスを感じやすいです。また、感覚的な体験や価値観を基に判断をするため、抽象的な概念や論理的な説明には馴染みにくい傾向があります。
自由度が高い職種や柔軟な働き方を選ぶことで、自分らしさを発揮しやすくなります。趣味や副業で自己表現の場を作るのも有効です。さらに、組織内でも創意工夫を行い自分の価値観を活かすことで、社会と調和しながら成長できるでしょう。
3位:INTP(論理学者)|社会適応に苦労しがち
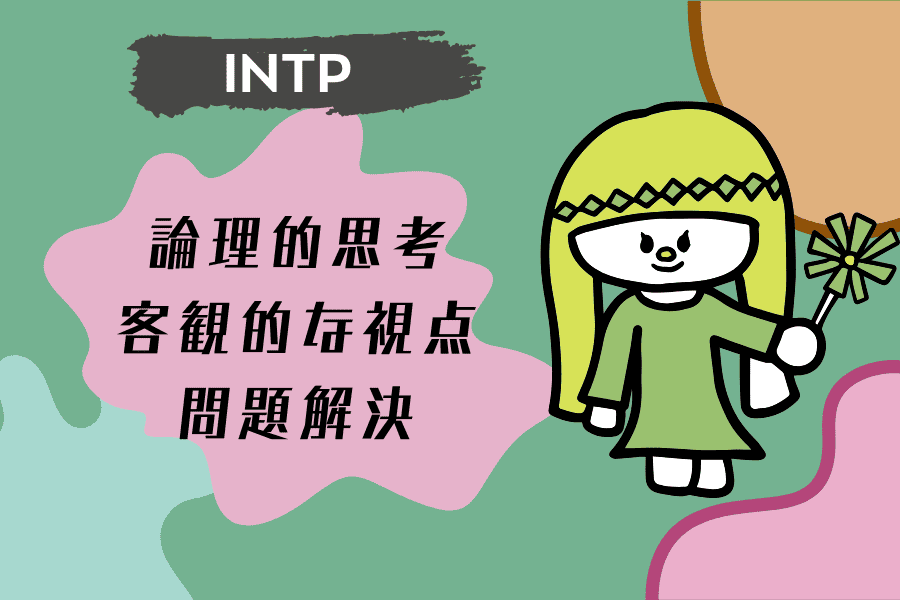
- 論理的思考や分析力に優れる
- 日常的なコミュニケーションで感情面を軽視しがち
- 社会の感情的側面とのギャップに苦労する
INTPは論理的思考と分析力が強みであり、抽象的な理論や概念を重視する特徴があります。しかし、日常的な会話で感情面を軽視してしまうことが多く、意図せず相手を不快にさせる場合があります。また、感情を重視する社会的な側面とのギャップにより、社交的な場面で居心地の悪さを感じることもあります。
社会適応力を高めるためには、論理的思考を活かせる分野に集中することが有効です。また、心理学や社会学を学び、感情的な側面への理解を深めるのも効果的です。さらに、自分の考えを分かりやすく伝える練習を行うことで、周囲との調和を図りやすくなるでしょう。
4位:INFJ(提唱者)|完璧主義で疲弊しやすい
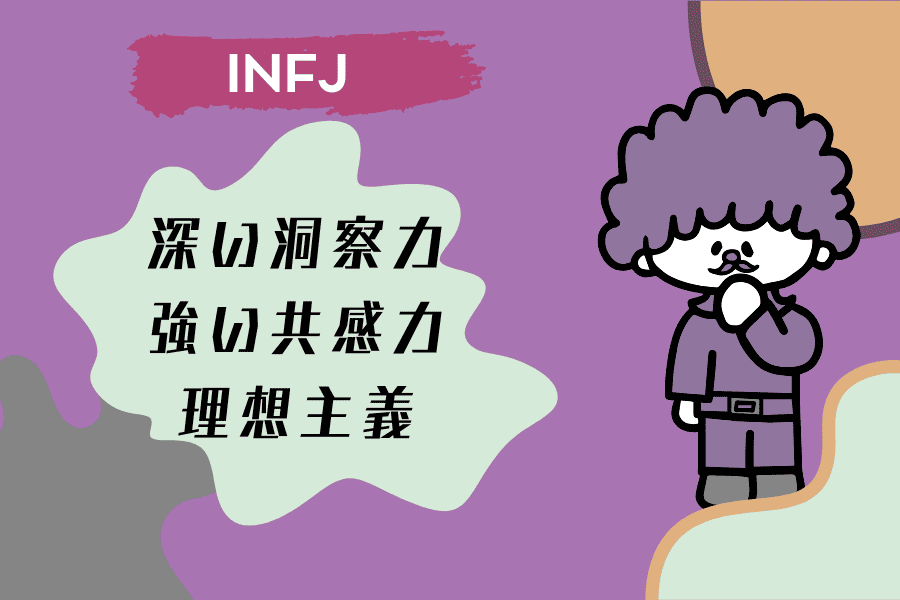
- 完璧主義的な傾向があり、自己批判をしやすい
- 他者の期待に敏感で、自分を見失いやすい
- 洞察力と共感能力を活かしやすい
INFJは完璧主義的な性格から、些細なミスでも自分を厳しく批判してしまう傾向があります。この習慣は精神的な疲労や自信喪失につながりやすいです。また、他者の期待に敏感で、それに応えようとするあまり自分本来の姿を見失うことがあります。特に周囲の期待が大きい場合、その負担がストレスとなることが多いです。
自己批判を適度に抑え、ありのままの自分を受け入れる姿勢を持つことが重要です。他者の期待と自分の価値観のバランスを取ることも大切です。洞察力や共感能力を活かし社会貢献の場を見つけることで、自己肯定感を高めながら社会と調和する道を探りましょう。
5位:INTJ(建築家)|他者との協調が難しい
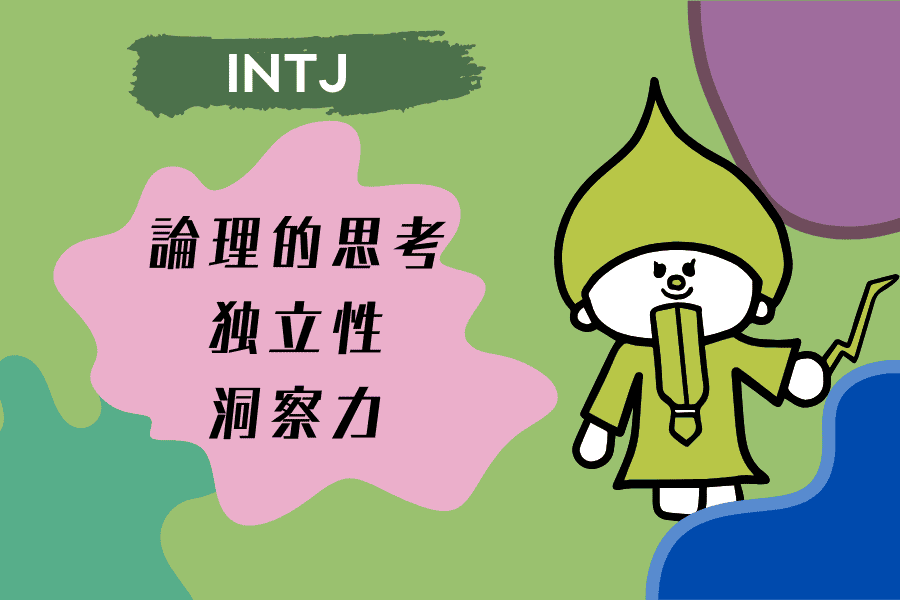
- 効率と論理を重視し、感情的要素に苦手意識を持つ
- 自身の考えに自信を持ち、他者の意見を軽視しがち
- 洞察力と問題解決能力を強みとして活かせる
INTJは効率や論理を重視する性格から、感情的な要素を含む人間関係に苦手意識を持つ傾向があります。例えば、非効率的だと感じた意見を即座に却下することで、他者との協調を損ねてしまう場合があります。また、自身の考えに強い自信を持つため、他者の意見を軽視しがちな点も協調を難しくする要因です。
他者の意見を聞く時間を意識的に設けることが対人スキルの向上につながります。さらに、感情的側面への注目や共感力を養うことで、他者との信頼関係を築きやすくなります。自身の考えを丁寧に伝える努力を重ねることで、社会適応力を高めながら持ち前の洞察力を活かせるでしょう。
6位:ENFP(広報運動家)|集中力や継続性に欠ける
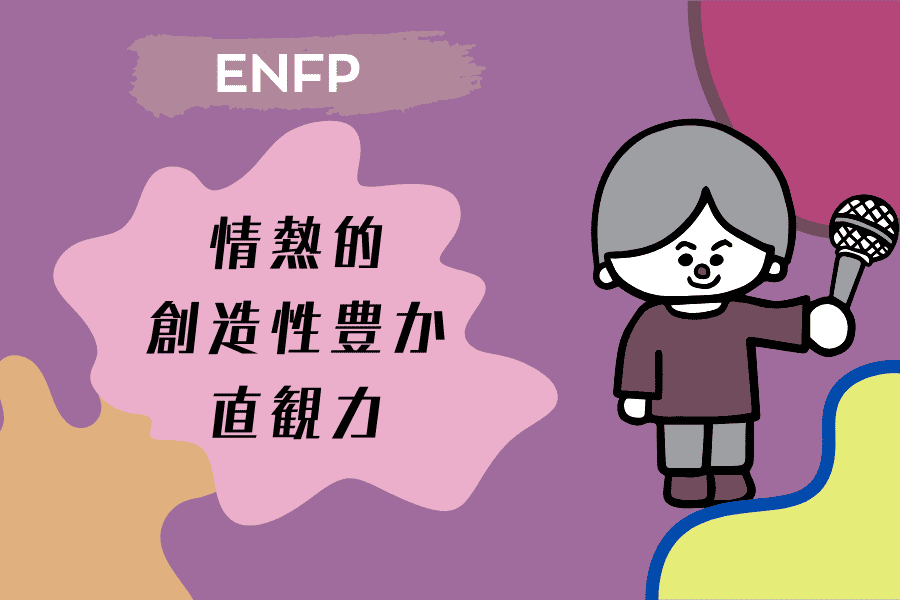
- 創造性と熱意にあふれるが、一つの課題に集中しづらい
- 興味が多岐にわたり、途中で他のアイデアに心を奪われやすい
- 短期目標や工夫を通じて継続性を高めることが可能
ENFPは創造性と熱意でプロジェクトをスタートさせる力に優れていますが、一つの課題に集中し続けることに課題を抱えやすいです。新しい興味やアイデアに引き込まれ、元の取り組みが中途半端になることがあります。この傾向は、多様な興味や柔軟な思考が原因です。
短期目標を設定し、小さな成功を積み重ねることが効果的です。また、進捗を定期的に振り返り、モチベーションを維持する工夫を取り入れると良いでしょう。作業に創造的な要素を加えたり信頼できる人に進捗を報告する場を作ったりすることで、集中力と継続性を向上させながら成果を安定させることができます。
7位:ISTP(巨匠)|独立心が強く協調性に欠ける
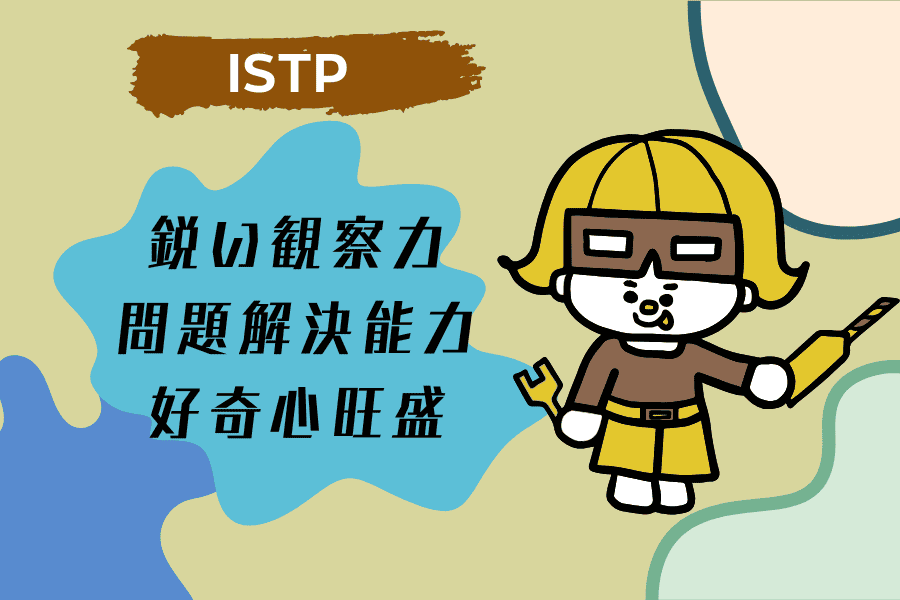
- 独立心が強く、チームで孤立しやすい
- 論理を重視し、感情的な対人関係に馴染みにくい
- 問題解決能力を活かし、協調性を高める余地がある
ISTPは独立心が強く自分の役割に集中するため、チーム内で孤立しやすい傾向があります。感情的な交流に苦手意識を持つため、論理的な対応がかえって人間関係を難しくする場合があります。特に指示に疑問を感じたとき、それを率直に表現することが摩擦の原因になりやすいです。
しかし、問題解決能力と適応力を活かせば、チームへの貢献を高めることができます。相手の意見を積極的に聞く姿勢を持ち、共感を示す表現を意識することが重要です。自分の専門性をチーム目標にどう活かすかを提案することで、協調性を高められるでしょう。
8位:ENTP(討論者)|対人関係でトラブル多い
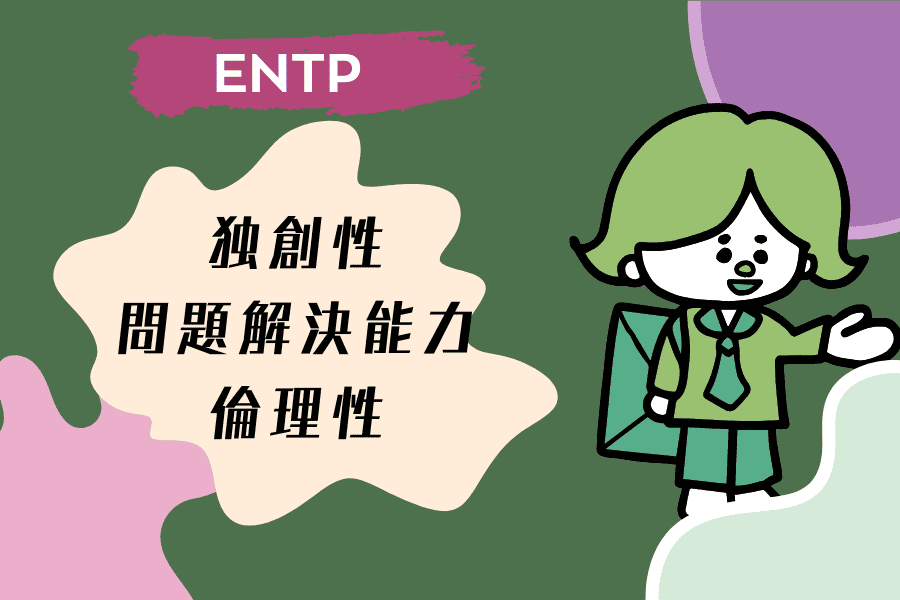
- 議論好きな性格が対人関係の摩擦を生みやすい
- 固定的な組織構造や決定プロセスに不満を感じやすい
- 柔軟な思考力を活かしつつ、対人スキルを向上させる余地がある
ENTPは議論を好む性格が原因で、対人関係で摩擦が起こりやすい傾向があります。特に、既存のアイデアや方針に批判的な意見を述べた際に、相手を不快にさせてしまう場合があります。また、固定的な組織構造や決定プロセスに不満を感じやすく、上司や同僚から反抗的だと誤解されることも少なくありません。
ただし、柔軟な思考力と創造性を活かせば、対人関係を改善することができます。批判的な意見を述べる際には、相手の立場を考慮しつつ具体的なメリットを提示すると良いでしょう。建設的な議論を心がけ相手の意見にも耳を傾ける姿勢を示すことで、より良い人間関係を築ける可能性が高まります。
MBTIで見る社会不適合ランキング 9位~16位
MBTIの9位から16位に位置する性格タイプの社会適応における課題を探ります。各タイプの特徴的な強みと、それが時に社会不適合につながる可能性を解説します。
また、それぞれの性格タイプが持つ潜在能力を活かしつつ、課題を克服するための実践的なアプローチも提案していきます。
9位:ENFJ(主人公)|自己犠牲に陥りやすい
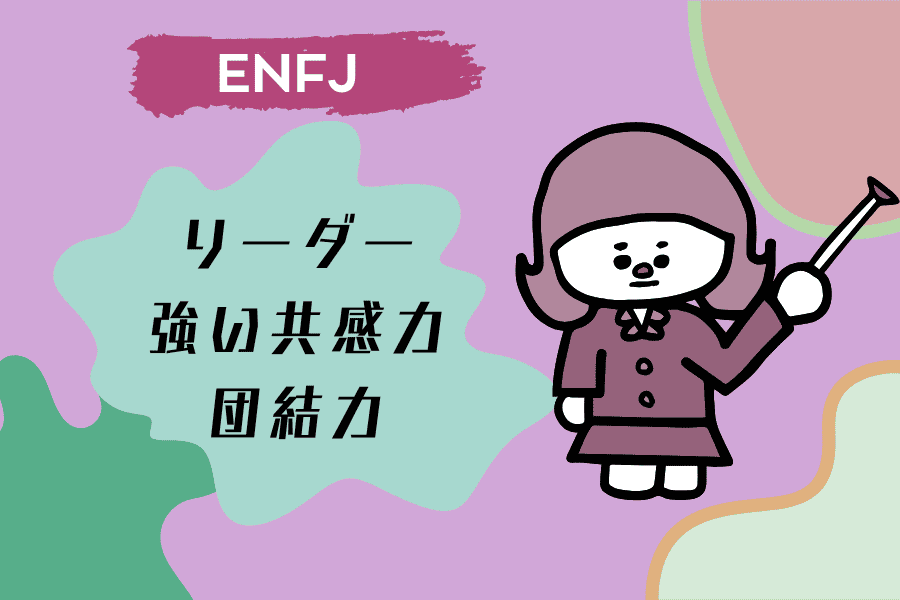
- 周囲の期待に応えようとしすぎて自己犠牲に陥りやすい
- 他者の感情や要求に敏感で、「ノー」と言うことが苦手
- 自己ケアと適切な境界線の設定が課題克服の鍵となる
ENFJは周囲の期待に応えたい気持ちが強いため、必要以上に自己犠牲をしてしまう傾向があります。他者の感情や要求に敏感であるため、自分の限界を超えた対応をしてしまい断ることが苦手です。この習慣は、長期的に見るとバーンアウトや精神的疲労の原因となり得ます。
自己ケアの時間を確保し、自分の感情や欲求を振り返る習慣を持つことが重要です。他者との適切な境界線を設定する勇気を持つことで、無理をしなくても良い人間関係を築ける可能性が高まります。これらの工夫により、ENFJは共感力を活かしながらより健全な社会生活を送ることができるでしょう。
10位:ENTJ(指揮官)|他者の感情への配慮不足
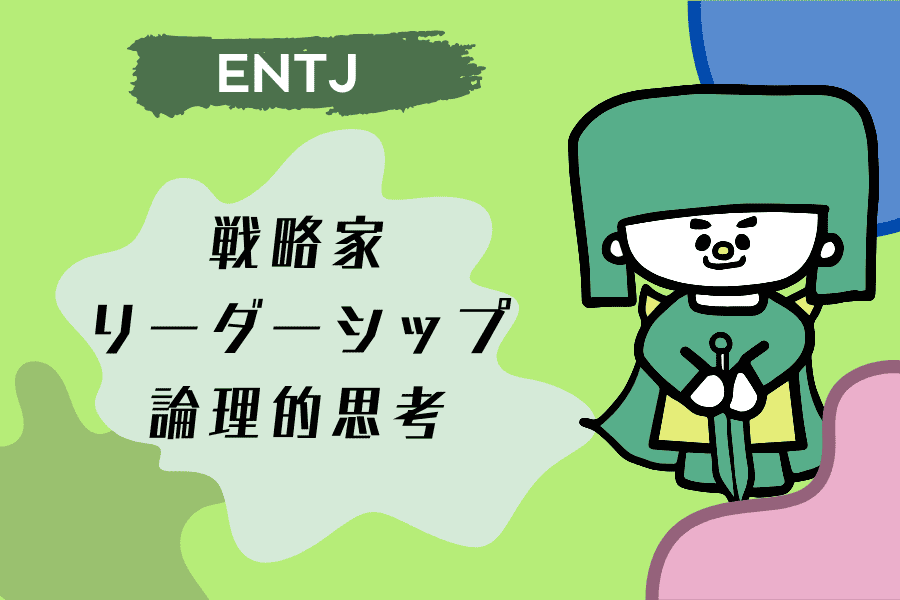
- 効率と成果を重視し、感情的配慮が不足しがち
- 他者の感情を非合理的と捉え、摩擦を生むことがある
- 感情知性を高めることで、リーダーシップを向上させられる
ENTJは効率と成果を追求する姿勢が強いため、感情的な配慮が不足する場面が多く見られます。特に、チームメンバーの感情的ニーズを軽視することで職場環境の雰囲気が悪化したり、人間関係に摩擦が生じたりすることがあります。感情を「非合理的」と捉える傾向が原因の一つです。
優れたリーダーシップには、感情知性を磨くことが不可欠です。積極的に部下の声に耳を傾け、個々の課題や悩みを把握する時間を設けると良いでしょう。チームメンバーの個性を理解し適材適所で配置することで、効率と成果を維持しつつ、より包括的なリーダーシップを発揮できるでしょう。
11位:ESFP(エンターテイナー)|長期目標達成が難しい

- 即座の満足感を優先し、地道な努力を後回しにしがち
- 締め切りや長期的な計画より、その場の楽しみを選びやすい
- 適応力と人間関係構築能力を活かせば長期目標も達成可能
ESFPはその場の楽しみを優先する傾向があり、長期的な目標達成に向けた努力を後回しにすることがあります。例えば、締め切りが迫っている仕事よりも友人との急な外出を選ぶケースが挙げられます。このような志向が、将来の成果のための計画や地道な努力を阻む要因となります。
ただし、ESFPの持つ適応力や人間関係構築能力は長期目標の達成にも役立ちます。小さな目標を設定して達成感を積み重ねたり、目標を友人と共有して支援を得たりする方法が効果的です。楽しみながら成長できる環境を作ることで、自然な強みを活かしつつ長期的な成功に近づくことができます。
12位:ESTP(起業家)|安定を求める環境に不適応
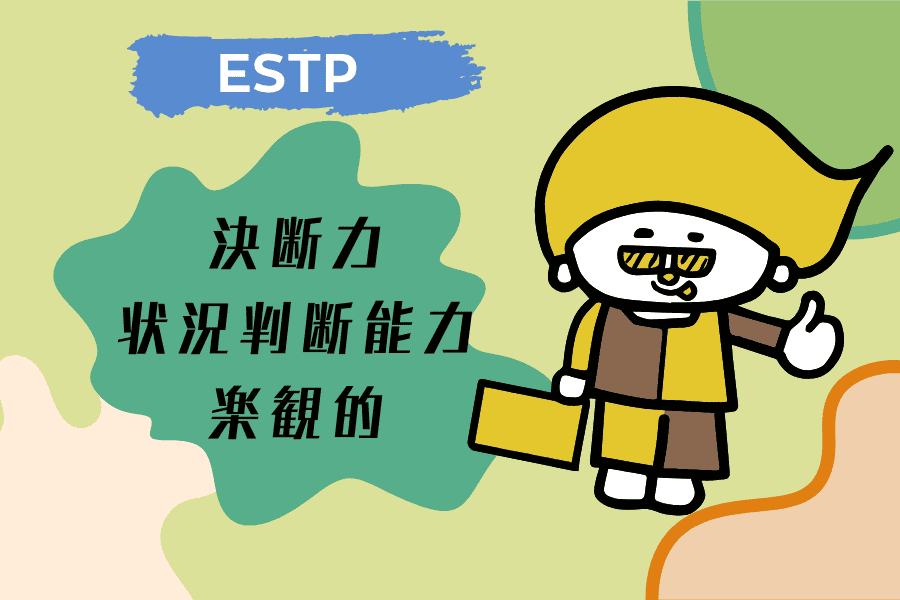
- 即断即決の傾向が慎重な環境で軋轢を生みやすい
- 長期的な計画より目の前の問題解決を重視しがち
- 短期成果と長期目標を意識することで適応力を高められる
ESTPの即断即決を好む傾向が、慎重な意思決定を求める環境では摩擦を引き起こすことがあります。例えば、金融や戦略部門のような長期的な計画が必要な場面では、目の前の問題解決に集中しすぎてチームの方向性とずれることがあります。安定志向の文化に対し違和感を覚えるため、能力を発揮しにくいと感じることもあるでしょう。
ただし、問題解決能力と適応力を活かせれば、こうした環境でも成果を上げることが可能です。短期成果と長期目標のバランスを意識し、慎重な分析と直感的な判断を組み合わせるスキルを磨くと良いでしょう。さらに、リスク管理や説得力のある提案方法を学ぶことで、安定志向の環境でも柔軟に適応できる可能性が高まります。
13位:ISFJ(擁護者)|自己主張が苦手
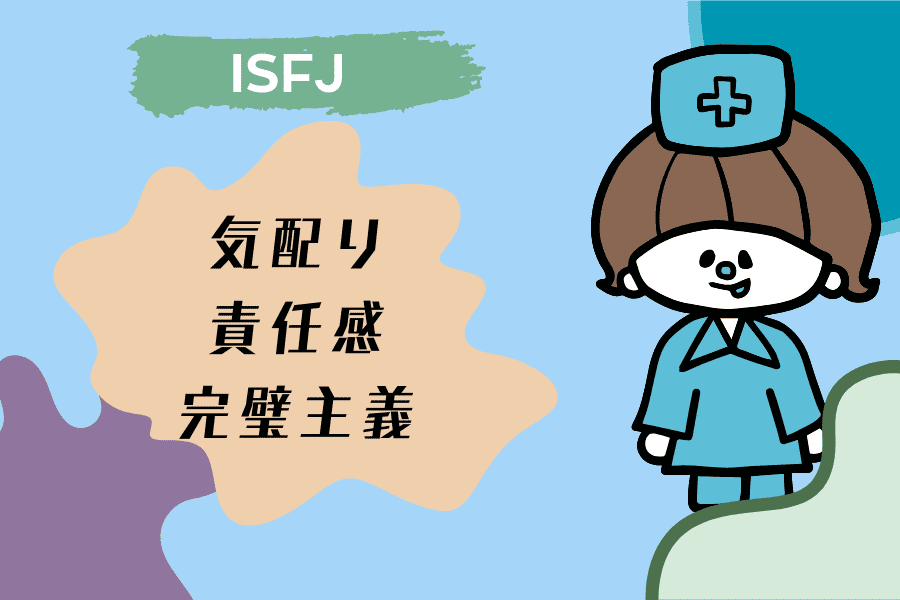
- 周囲の調和を優先し意見を抑えがち
- 自己主張で関係悪化を恐れる傾向がある
- 共感力を活かして意見を伝える練習が有効
ISFJは周囲への気配りと責任感が強く、人間関係の調和を重視します。そのため、自分の意見を伝える際に相手を不快にさせたり関係が悪化することを恐れる傾向があります。結果として、意見を遠慮がちにしたり伝えないまま終えたりする場合があります。
しかし、共感力や観察力を活かすことで、丁寧に自己主張をするスキルを磨けます。小さな場面での意見表明から練習を始め、成功体験を記録する習慣を作ると効果的です。意見を伝えることで関係が良好になる例を積み重ねると、自信を深めることができます。
14位:ESFJ(領事官)|自己決定に迷いが生じる

- 周囲の期待を気にしすぎて迷いやすい
- 他者からの承認を求めすぎる傾向がある
- 自己主張や価値観の明確化が課題
ESFJは周囲との調和を重視し、他者のニーズに敏感です。この特性は人間関係を円滑にしますが、自己決定の場面では迷いやすくなる要因にもなります。周囲の期待を気にしすぎるため、自分の本当の願望を見失う場合があります。
他者からの承認欲求や対立を避けたい心理が背景にあるため、選択肢を周囲に合わせる傾向が強いです。自己決定力を高めるには、自分の価値観を明確にし定期的に振り返ることが重要です。「ノー」と言う練習や信頼できる人との相談も有効です。
15位:ESTJ(幹部)|変化への適応が難しい
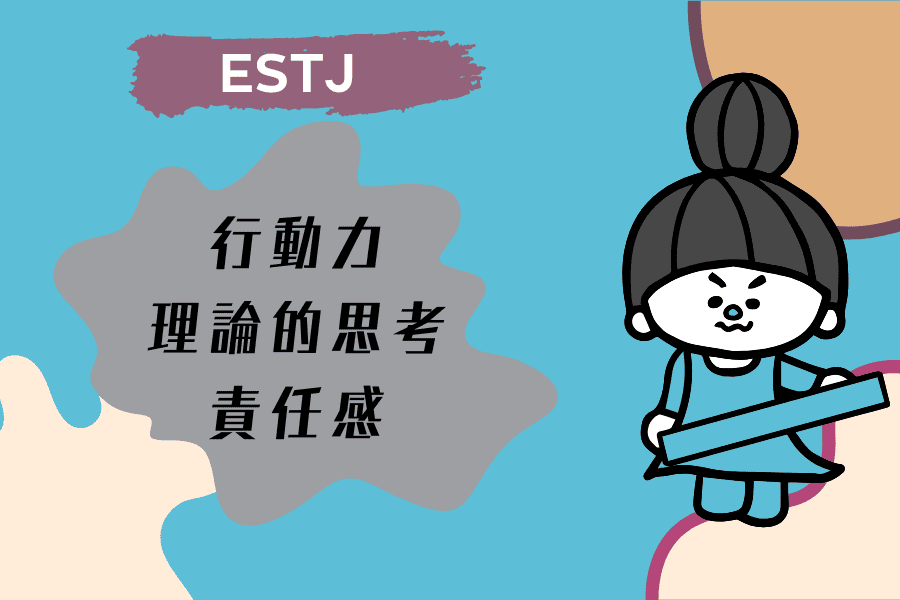
- 長年のプロセス変更に抵抗を感じやすい
- 効率低下や混乱を受け入れるのが苦手
- 柔軟性を高める段階的なアプローチが有効
ESTJは秩序や伝統を重んじ、組織力と実行力に優れています。一方で、業務プロセスの大幅な変更や新しい技術の導入に直面すると、変化に対して抵抗を感じる傾向があります。効率性を重視するため、変化による一時的な混乱を受け入れにくいのが特徴です。
ただし、柔軟性は現代社会で欠かせない資質です。小さな変化を段階的に取り入れたり、客観的なデータに基づいて変化の必要性を理解したりすることが有効です。また、変化推進の役割を他者に任せることで、自身が得意とする安定性の確保に集中できるでしょう。
16位:ISTJ(管理者)|新しい方法の受入れが苦手
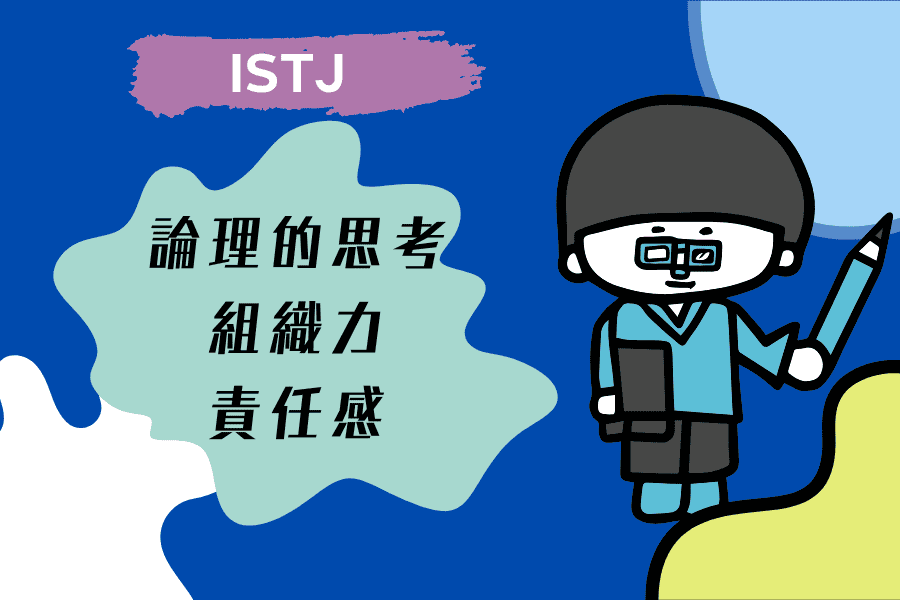
- 確立された手順や経験を重視する傾向がある
- 新しい方法に対するリスクへの警戒心が強い
- 段階的な導入や利点の数値化が効果的
ISTJは信頼性と組織力に優れ、職場で重要な役割を果たします。一方で、新しい方法の受け入れには苦手意識を持つ場合があります。確立された手順への信頼が強く、変化によるリスクや学習コストを警戒するためです。
柔軟性を養うには、段階的な導入や新しい方法の利点を数値的に示すことが有効です。試験的な導入期間を設けるとISTJの分析的な思考を刺激し、変化への抵抗を減らせます。また、既存の方法と新しいアプローチを比較する場を作ることで、効率性を重視するISTJも納得しやすくなるでしょう。
まとめ
MBTIと社会不適合の関係について、本記事では詳しく解説しました。各タイプの特徴や課題、そして社会適応のためのアドバイスをお伝えしています。
自分のタイプを知り、長所を活かしながら短所を克服することで、より充実した社会生活を送れるでしょう。MBTIは自己理解の道具として活用し、前向きな成長につなげていきましょう。